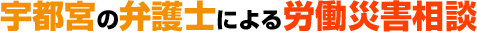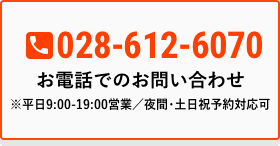建設現場で発生した労災と補償・賠償【労災に詳しい弁護士が解説!】
1.建設業・建設現場につきものである事故
建設業に従事される方が、建設現場で勤務中にケガをしてしまうという事例は、少なくありません。建設業は、他業種にくらべて重いものや重機をよく用いるため、比較的重いけがをしてしまいやすいことも特徴です。また、屋外で勤務することにより、屋内勤務に比べて様々なリスクにさらされていることも事実です。
建設現場における事故が重大な場合には死亡災害も起こりやすいというのも特徴といえます。仮設物や建築物からの墜落・転落、それらの崩壊・倒壊、動力運搬機の稼働等、建設現場は多くのリスクを伴います。
また、建設業には、発注者や元請業者、下請業者等、工事の規模や内容によって、さまざまな業者が関係しており、作業員がケガをした時の責任の所在が分かりにくいといった特徴もあります。労働災害にあってしまった場合は、労災保険からの給付が受けられるほか、治療費・後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。本記事では、建設業に従事される方が業務中にケガを負う等の事故が発生した場合の、労災認定や損害賠償について解説いたします。
2.ケガが労働災害によるものと認定される流れ
要件
ケガ等をしてしまったことが労働災害によるものであると認定されるためには、労働者の負傷・疾病などが、「業務上の事由」(労働者災害補償保険法1条)によって発生しているといえることが必要です。
では、「業務上の事由」といえるかどうかは、どのように判断するのでしょうか。
これについては、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要素が含まれている事故であったかどうかによって決まります。
まず、労働者が労働関係の下にあった場合に起きた災害であれば、「業務遂行性」の要素があると判断されます。
要するに、従業員として仕事中の事故でないといけないということです。
判断に迷う例として、就業中にトイレに行く時間や、出張中仕事をしている時間が考えられますが、これらはいずれも業務遂行性の要素があると判断された裁判例があります。
次に、業務遂行性があることを前提として、業務と負傷の間に因果関係があるといえるならば、「業務起因性」の要素があると判断されます。
業務に関係する作業をしている際にケガをしてしまったのであれば、業務と負傷の間に因果関係があると判断されることが通常です。
一方、業務中、業務とは無関係に行っていた私的な行為によって傷害を負ったのであれば、因果関係が否定され、「業務起因性」の要素がないと判断されます。
労災を認定する手続きの流れ
労災の認定は、一次的には、労災保険制度の中で行われます。
したがって、労災保険給付を担う労働基準監督署へ、申請を行うことになります。
どの労働基準監督署かというと、会社の所在地を管轄する労働基準監督署になります。
申請についてのルールは、厚生労働省のホームページで詳しく説明されています。
>>厚生労働省のホームページはこちら
3.労災認定がされた場合、労災保険から受けられる給付
労災認定がされた際、労災保険制度により受けられる給付には以下のようなものがあります。
療養(補償)給付
療養(補償)給付は、怪我をしてしまったり病気にかかってしまった際の治療費を給付するものです。
診察費用、検査費用、画像撮影費用、薬剤料、処置費用、手術費用、入院費用等が対象となります。
この給付は、病院に対して直接給付される、すなわち労災にあってしまった人の窓口負担がなくなるという形で実現するのが原則です。
休業(補償)給付
休業(補償)給付とは、労災事故によって働けなくなってしまった期間の給料を補填する役割を持つ給付です。
具体的には、療養中で休業している期間の4日目から支給が開始されます。
給付される金額は、1日につき、給付基礎日額の6割が支給されます。
ただし、休業の必要性が認められ、かつ、実際に休業していることが条件となります。
障害(補償)給付
障害(補償)給付とは、労災事故により後遺障害が残存したと認められた場合に、その残存した後遺障害の程度に応じて給付される性質のお金です。
障害(補償)給付の給付額を判断する基準は、定型的なものとなっており、後遺障害の程度に応じた給付が受けられます。
後遺障害の程度は1級~14級に分類されており、1級から順に重いものとなっています。
障害(補償)給付は、一時金と年金の二種類に分かれており、8級~14級の場合は一時金の給付のみが、1級~7級の場合は年金の給付が受けられます。
4.労災保険以外からの損害賠償の可能性
労災保険の役割
先に述べた労災保険は、労働者に対し国が最低限の補償を用意したものであって、労災の発生が会社や他の従業員によるものでないときも給付されるものである一方、損害のすべてを補填するのに十分な制度にはなっていません。
会社等に対する損害賠償
仮に、労働災害が会社や他の従業員の故意・過失によって生じたものである場合は、会社に対する損害賠償が可能となります。
この損害賠償請求は、損害のすべてについて請求を行うことが可能です(ただし、労働者にも過失が認められる場合は、過失相殺と言って、損害のうち一定割合の賠償責任が控除される可能性があります。)。
労働災害が会社や他の従業員の故意・過失によって生じた場合というのは、法律用語でいえば、会社に不法行為責任または安全配慮義務違反が認められる場合をいいます。
責任の所在について
初めに述べたように、建設現場では、複数の業者が関係しているパターンが多く、責任の所在は一見分かりづらいものとなっています。
この記事では、下請業者、元請業者、発注者の三種類に分け、それぞれの者が負う責任ついて解説します。
下請業者
下請業者は、最終的に建設現場で作業を行う会社であり、下請業者とその従業員(作業員)には、雇用契約の関係がある場合が多いでしょう。そのような場合は当然、下請業者は従業員(作業員)に対して直接、安全配慮義務(労働契約法5条)を負いますから、現場での危険防止のための必要措置・安全対策をする義務があります。
したがって、これらの義務に違反して事故が発生した場合は、負傷者に対して損害賠償責任を負うといえるでしょう。
元請業者
作業員は、元請業者に雇われているわけではない場合が多いでしょう。そうすると、上記のように雇用契約を根拠として安全配慮義務があるということは難しそうです。
しかし、安全配慮義務は、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間」にも、信義則上認められるものであると判断された事例があります。「特別な社会的接触の関係」というのは、
例えば、建設現場でいえば、元請業者が現場の作業を監督して具体的に指示を出していたり、事故の原因となった道具が元請業者の管理するものであったり、実質元請業者のやり方で作業をしていた場合をいいます。このような場合には「特別な社会的接触の関係」に入ったといえる可能性があるでしょう。
よって、元請業者が作業員に対して安全配慮義務を負うことになりますので、これに違反して事故が発生した場合は、責任を問うことができるということになります。
発注者
発注者については、元請業者以上に作業員との距離が遠い存在ですが、元請業者の解説で述べたような関係にあるならば、同様に安全配慮義務が肯定される可能性はあります。
請求の方法
労働者が会社等に対して上記損害賠償を請求する方法は、①自ら会社と交渉を行う、②弁護士に依頼して交渉・訴訟を行ってもらうというものが考えられます。
①は、一見安価で手軽に済むように思えますが、労働者自ら、「会社等に不法行為責任または安全配慮義務違反が認められる」ということを主張・立証し、損害賠償を請求するということのハードルは非常に高いです。特に、元請業者や発注者に責任を追及するためには、緻密な論理構成が必要となるでしょう。
仮に相手が責任を認めたとしても、具体的に適正な損害額はいくらかを算定することが難しいですし、どのような証拠を出せばいいのかも複雑です。会社によっては、労働者が交渉を申し出たところで、相手にしない場合もあるでしょう。
一方、②は、弁護士費用以上の見返りが得られるケースが多いと言えます。知識・経験が豊富な専門家が行う賠償請求は、損害額として適正な範囲かつ最大のラインが見えますし、訴訟のプロである弁護士であれば立証活動も慣れています。また、会社としても、弁護士の請求に応じなければ法的手段がとられてしまうことが目に見えている以上、相手にしないわけにもいかなくなります。
5.まとめ
本記事では、建設業に従事される方が業務中にケガを負う等の事故が発生した場合の、労災認定や損害賠償について解説しました。
労災申請や賠償請求については、さまざまなルールやハードルがある一方、適切にこれを行使することができれば、損害を補うための賠償を受けることができます。
満足のいく賠償を受けるためにも、専門家である弁護士に、一度相談してみてはいかがでしょうか。